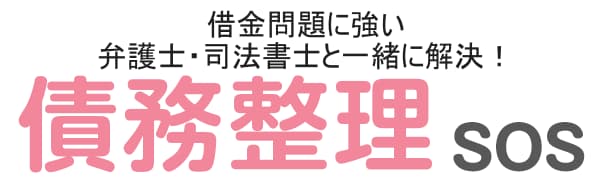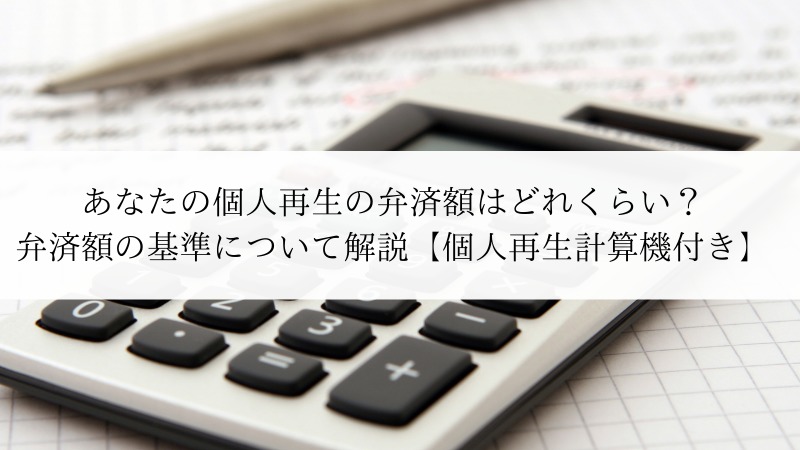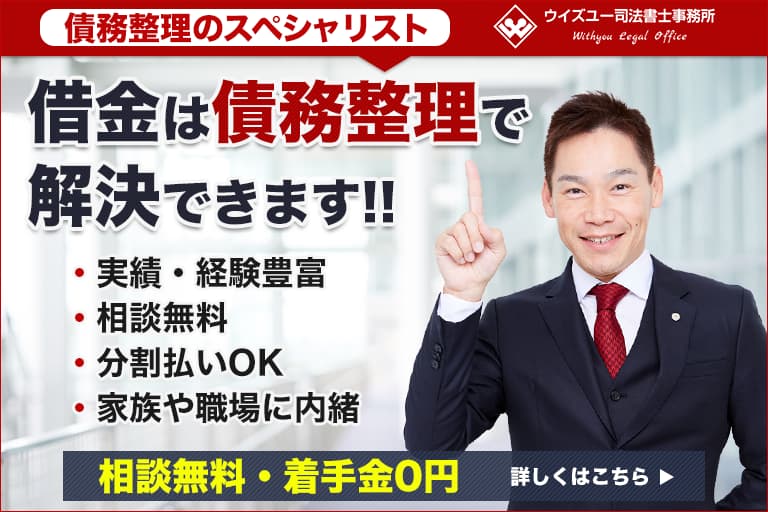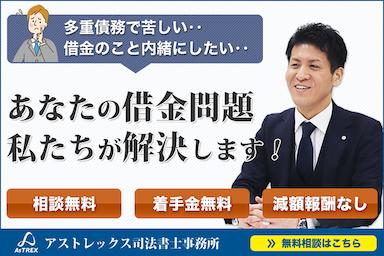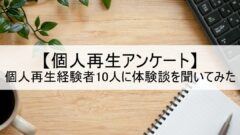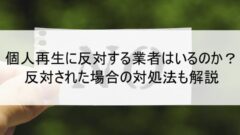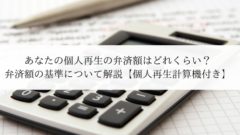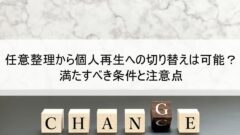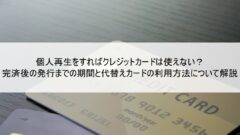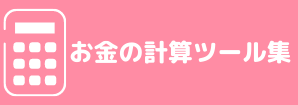- 個人再生で最低限支払わなければならない金額がわかる
- 最低弁済額が支払えないときの対処法がわかる
- 最低弁済額を下げるためにやってはいけないことがわかる
- 弁護士・司法書士のサポートで最低弁済額を抑えられる可能性がある
個人再生は借金問題解決のために国が定めた手続きであり、現在多くの人が利用しています。裁判所の決定によって借金が大幅に減額され、減額後の借金を3年~5年で返済していくことになります。
そこで気になるのは、個人再生をすると最低限いくら返済しなければならないのかということでしょう。個人再生における最低弁済額は、事案によって異なります。確実に返済していくためには、最低弁済額がいくらになるのかを事前に知っておくことが大切です。
この記事では、個人再生における最低弁済額の計算方法をわかりやすく解説していきます。また、【個人再生計算機】で弁済額を概算することもできますのでご活用ください
【個人再生計算機】で弁済額を計算してみよう
個人再生計算機を使って「個人再生するとあなたの借金はいくらになるのか」「毎月いくら返済するのか」を計算してみましょう。
個人再生をお考えの方はぜひ参考になさってください。
【計算機の使い方】
*STEP1:以下の各項目に金額を半角数字で入力
*STEP2:計算ボタンをクリック
| 予想される合計返済額 | {{goukei}}万円 |
|---|---|
| 予想される毎月の返済額 (返済期間が3年間で36回払いの場合) |
{{maituki}}万円 |
*東京地方裁判所の資料を基に作成されています。
(注)計算結果はあくまで目安です。実際の返済額は再生者個人の状況・事情や手続き行う裁判所によって変動することがあります。そのため、正確な数値を知りたい場合は弁護士・司法書士に相談しましょう。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所の手続きを通して借金を減額し、残額を返済計画に従って返済していく債務整理の方法です。今日では、多重債務を抱えている人を中心に多くの人が利用しています。
個人再生は、任意整理と比べると大幅な借金減額が可能となる一方で、手続きの内容は煩雑であり、手間がかかります。また、自己破産と比べると、マイホームやマイカーといった物を含めてほとんどの財産を失わなくても済む一方で、借金の減額は部分的なものに留まるため、返済自体は続けなければならない手続きです。
個人再生の最低弁済額とは
個人再生は民事再生法で定められている手続きであり、同法では「最低限この金額以上は返済しなければならない」という基準が定められています。これが最低弁済額というものです。
民事再生法で定められている最低弁済額の基準には、次の3種類があります。
-
- ①借金総額に応じた最低弁済基準
- ②清算価値保証基準
- ③可処分所得基準
個人再生の手続きには、主に自営業者向きの「小規模個人再生」と主にサラリーマン向きの「給与所得者等再生」とがあります。この2種類の手続きで最低弁済額の決定方法は以下のように異なります。
- 小規模個人再生:①と②のどちらか高い方
- 給与所得者等再生:①~③のうち最も高いもの
では、3つの基準について詳しくみていきましょう。
個人再生で実際に支払う返済額の計算方法
個人再生で実際に支払う返済額を計算する際は、以下の方法で最低弁済額を割り出していきます。
借金総額に応じた最低弁済基準
まず、民事再生法では借金総額に応じて最低限返済しなければならない金額が以下のとおり定められています。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円以上~500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上~1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円以上~3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円以上~5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
例えば、借金総額が700万円であればこの基準による最低弁済額は140万円(700万円×1/5)となります。
清算価値保障基準
個人再生では、「清算価値保障の原則」を守る必要があります。清算価値保障の原則とは、自己破産をした場合に没収される自己所有の財産の全体の価値に相当する金額については最低限弁済しなければならないという決まりのことを言います。
ここでいう財産とは、車、家、株式などの有価証券、保険の解約返戻金などの全ての財産を含みます。この制度は、個人再生では自己破産のように財産の没収はされない代わりに、その財産を現金化したときの金額はせめて返済する義務を課し、債権者の保護を図る目的で採用されています。
例えば、時価100万円の車、100万円分の株式、50万円の現金を持っている場合、清算価値は「100万円+100万円+50万円=250万円」ということになります。これが、この基準による最低弁済額となります。
可処分所得基準
給与所得者等再生では、「可処分所得」を計算する必要があります。可処分所得とは、給料の全額から生活費や税金、保険料等を差し引いた後の金額のことで、言い換えると、自由に使える収入のことを言います。
そして、「可処分所得の2年分」がこの基準による最低弁済額となります。注意が必要なのは、収入から差し引く生活費等は実際の支出額ではなく、生活保護の基準を参照して裁判所が決めている金額となることです。
つまり、最低生活費を差し引いた後に残る収入はすべて返済に充てなければならないということになります。そのため、給与所得者等再生では小規模個人再生よりも最低弁済額が高くなる傾向にあります。
例えば、1ヶ月の可処分所得が15万円の場合、可処分所得の2年分は360万円(15万円×24ヶ月)となり、360万円がこの基準による最低弁済額となります。
個人再生における最低弁済額の具体例
では、具体例を挙げて最低弁済額を実際に計算してみましょう。
めぼしい財産がないケース
借金総額:500万円
所有財産の総額:10万円の預貯金のみ
希望する手続き:小規模個人再生
小規模個人再生を申し立てる場合は可処分所得基準は考慮する必要がありませんので、他の2つの基準のみで最低弁済額を計算します。
| 借金総額に応じた最低弁済基準による最低弁済額 | 100万円 |
|---|---|
| 清算価値保証基準による最低弁済額 | 10万円 |
最終的に、最低弁済額は両基準の高い方である100万円となります。
高額の財産を所有しているケース
借金総額:300万円
所有財産の総額:50万円の預貯金、時価50万円の車、解約返戻金見込額50万円の生命保険
希望する手続き:小規模個人再生
このケースも小規模個人再生ですので、以下の2つの基準のみで最低弁済額を計算します。
| 借金総額に応じた最低弁済基準による最低弁済額 | 100万円 |
|---|---|
| 清算価値保証基準による最低弁済額 | 150万円 |
最終的に、最低弁済額は両基準の高い方である150万円となります。後者の基準額が前者の基準額を超える場合には、所有財産の総額が高くなればなるほど最終的な最低弁済額も高額となることに注意が必要です。
収入が高いケース
借金総額:500万円
所有財産の総額:10万円の預貯金のみ
希望する手続き:給与所得者等再生
1ヶ月当たりの可処分所得:5万円
このケースは給与所得者等再生ですので、3つの基準すべてを考慮する必要があります。
| 借金総額に応じた最低弁済基準による最低弁済額 | 100万円 |
|---|---|
| 清算価値保証基準による最低弁済額 | 10万円 |
| 可処分所得基準による最低弁済額 | 120万円 (1ヶ月5万円×24ヶ月) |
最終的に、最低弁済額は3つの基準のうち最も高い120万円となります。仮に小規模個人再生であれば最終的な最低弁済額は100万円ですが、給与所得者等再生を選択することによって最低弁済額が増えたことになります。
最低弁済額を支払えないときの対処法
個人再生の申し立て前に最低弁済額を試算した結果、高額となって支払いきれないということもあるでしょう。そんなときは、以下のように対処しましょう。
小規模個人再生を選択する
給与所得者等再生を選択すると、小規模個人再生を選択した場合よりも最低弁済額が高くなるケースがほとんどです。サラリーマンやOL、アルバイト、パートなどの給与所得者でも小規模個人再生を選択することは可能ですので、可能な限り小規模個人再生を選択しましょう。
給与所得者等再生を選択するメリットがあるのは、小規模個人再生における書面決議で多くの債権者が反対意見を提出することが見込まれる場合のみです。今のところ、反対意見を提出する債権者は数少ないので、あえて給与所得者等再生を選択する実益がないケースが多くなっています。
ただ、少数ながら書面決議で反対意見を提出する債権者は実際にいますし、近年は少しずつ増えてきている傾向もあります。手続きを選択する前に弁護士または司法書士に相談し、見通しを確認することをおすすめします。
5年の分割払いを申請する
個人再生による返済期間は原則として3年(36回払い)ですが、それで返済が難しい場合には最長で5年(60回払い)までの返済期間が認められる可能性があります。
例えば、最低弁済額が300万円の場合、36回の分割払いでは毎月約8万4,000円を返済しなければなりませんが、60回の分割払いが認められれば毎月5万円の返済で済みます。
家計収支表などによって「3年での返済は難しいが5年なら返済できる」ということが説明できれば、基本的に5年の分割払いが認められます。
自己破産を申し立てる
以上の対処法によっても返済が見込めない場合は、そもそも個人再生の利用が認められません。そのため、自己破産を申し立てることになります。
自己破産をすると、一定の評価額を超える財産を処分しなければならないなどのデメリットはありますが、すべての借金の返済義務を免除してもらうことが可能です。
自己破産は最終手段ではありますが、個人再生の申し立てが難しい場合にはメリットが大きい制度なので、検討してみましょう。
個人再生の返済開始後に支払えなくなったときの対処法
個人再生による最低弁済額の返済が見込まれる状態で、再生計画案が無事認可されたとしても、返済開始後に何らかの事情で返済できなくなることもあるでしょう。
その場合には、以下の対処法が考えられます。
返済期間の延長を申請する
やむを得ない事情で返済の継続が難しくなった場合には、裁判所に「再生計画変更の申立て」を行うことで最大2年間、返済期間を延長してもらうことが可能です。やむを得ない事情の具体例としては、以下のようなものが考えられます。
- 失業や勤務先の業績不振による収入の減少
- 家族の病気やケガの療養による支出の増大
- 妊娠、出産、育児などのために働けない
返済期間の延長が許可されると、最低弁済額は変わりませんが、毎月の返済額が減るので負担が軽減されます。
ハードシップ免責を申請する
ハードシップ免責とは、返済期間の延長では対処できない場合で、最低弁済額4分の3以上を返済済みである場合に、裁判所への申し立てによって残りの返済を免除してもらえる制度のことです。
ただし、ハードシップ免責が許可されるためには、その他にも「債務者本人に責任のない事情で返済の継続が極めて困難となったこと」をはじめとして、厳しい条件を満たす必要があります。
ハードシップ免責が可能かどうかは、弁護士または司法書士に相談して確認することをおすすめします。
自己破産に切り替える
返済期間の延長もハードシップ免責も認められず、返済が滞ると裁判所によって再生計画が取り消されます。そうすると個人再生はなかったことになり、申し立て前の借金がそのまま残ることになります。
実際には返済した金額が差し引かれますが、それ以上に遅延損害金の加算によって借金総額が膨らんでいるはずです。
こうなると到底返済できないでしょうから、最終手段として自己破産に切り替えることになります。
最低弁済額を下げるためにやってはいけないこと
最低弁済額を下げるために、収入や財産を実際よりも少なく申告したり、事前に財産の名義変更をしたいと考える人もいるかもしれません。しかし、これらの行為は絶対に行わないでください。
虚偽の申告や財産隠しをしても再生計画案は認可されませんし、認可後に発覚すると取り消されます。それだけでなく、詐欺再生罪として刑事罰の対象にもなります。
最低弁済額を下げたいと考えるのは当然ですが、手続きは公正に行わなければなりません。
最低弁済額を低く抑えるには弁護士・司法書士に相談を
最低弁済額を低く抑えるためには、弁護士または司法書士といった法律の専門家に相談することを強くおすすめします。
個人再生手続きの運用は裁判所によって異なる部分もあり、専門家は地元の裁判所における運用を熟知しています。
例えば、一部の裁判所では、所有財産のうち99万円以内の現金と20万円以内の他の財産は清算価値に含めないという運用をしているところもあります。100万円の預金がある場合なら、事前に80万円を引き出し、80万円の現金と20万円の預金という形にしておくことで清算価値をゼロにできるので、最低弁済額を下げられる可能性があります。
その他にも、専門家はさまざまなノウハウを有していますので、最低弁済額が気になるのであれば相談してアドバイスを受けましょう。
まとめ
個人再生における最低弁済額は民事再生法で定められていますが、事前の対処によって下げることが可能な場合もあります。
ただし、虚偽の申告や財産隠しなどの不正行為は決して行ってはなりません。正しいノウハウで対処することが必要です。
弁護士・司法書士による正しいサポートを受けて、個人再生を成功させましょう。
また、本記事の【個人再生計算機】は、弁済額の目安として補助的に使用していただけると幸いです。