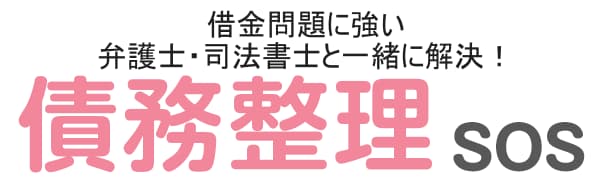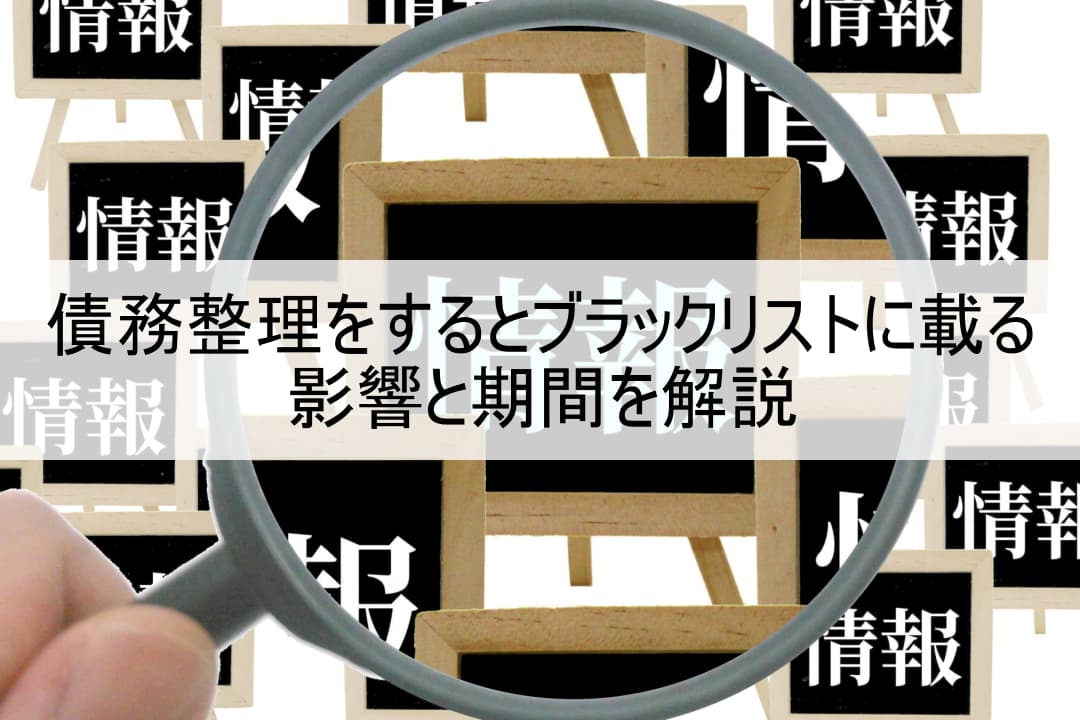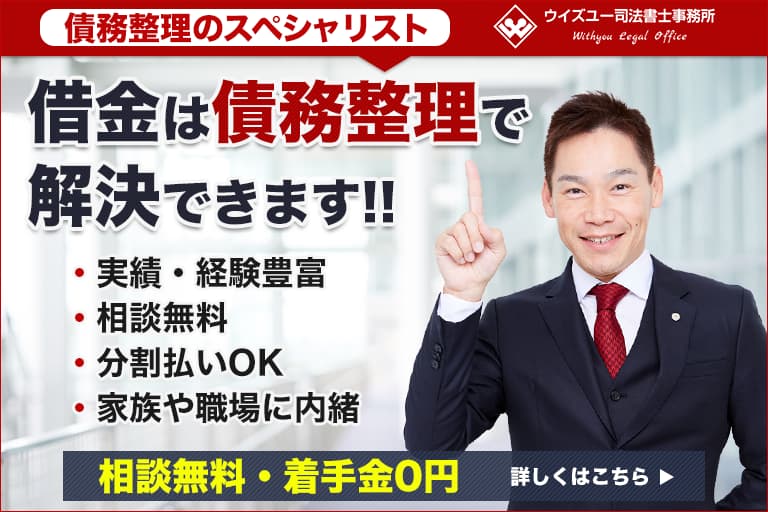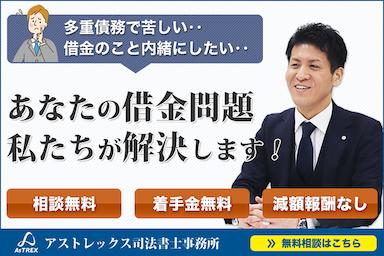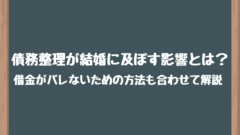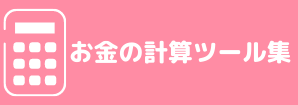- 債務整理をするとブラックリストに載る(約5年〜7年)
- ブラックリストに載るとは、信用情報機関に事故情報が登録されること
- ブラックリストに載るとローンが組めない、クレジットカードが使えない

この記事はこのような方にオススメです!
- 債務整理による「ブラックリスト入り」の基本情報を知りたい方
- ブラックリストに掲載されると発生するデメリットを知りたい方
- デメリットを最小限に抑える方法を知りたい方
「債務整理」をすると、ブラックリストに載りますが、それが嫌で先延ばしにしている方は多いようです。確かに、生活への影響は少なくありませんが、そのデメリットを最小限に抑える方法は存在します。
そこでこの記事では、以下の3点を詳しく解説します。
- ブラックリストと信用情報機関についての正しい知識
- ブラックリストから解除されるまでにかかる期間
- ブラックリスト入りのデメリットを最小限に抑えるために施せる対策方法

「ブラックリスト」の基本知識から、生活に及ぼすデメリットを最小限に抑える方法を一緒に確認しましょう!
債務整理をするとブラックリストに載る!
- 債務整理を行うとブラックリストに登録される
- ブラックリストに載るとクレジットカードが使えない等のデメリットが生じる
- 登録期間が過ぎればブラックリストから解除される
債務整理を行うと、信用情報機関という団体が管理するデータベースに債務整理を行った履歴が登録されます。
これがいわゆる「ブラックリストに載った」という状態です。
ブラックリストに登録されると、「クレジットカードの新規発行ができない」「ローンが組めない」といったデメリットが生じることになります。
ただし、永久にブラックリストに登録され続けるわけではありません。債務整理の種類によりますが、おおよそ5年〜7年ほど経過すればブラックリストから解除されます。
ブラックリストとは
ブラックリストと聞くと、クレジットやローンの返済で事故を起こした人たちの情報が一覧になってリスト化されたものをイメージする方が多いようです。しかし、実際にはそのような“リスト”は存在しません。
「延滞」「未払い」「債務整理」などの“返済事故”があった場合に、信用情報機関は「事故情報」としてその履歴を登録します。その情報が登録されている状態を「ブラックリストに載る」と言います。
| 登録される情報 | 事故情報(未払い、延滞、債務整理) |
|---|---|
| 情報の管理機関 | 信用情報機関(CIC、JICC、KSC) |
| 役割 | 個人の信用情報の収集と金融機関への情報開示 |
| 影響 | カード・ローンの契約、借入れの金額および可否 |
| 期間 | 任意整理は約5年、個人再生・自己破産は約7年 |
ブラックリストを管理する「信用情報機関」とは
ブラックリスト(事故情報)を管理しているのが信用情報機関です。
信用情報機関は、会員であるクレジット会社や金融機関から個人の取引内容の情報提供を受け、それらの信用情報をデータ化します。そして、会員の金融機関から個人情報の照会を受けた際に開示を行うのが役割です。
貸金業者など金融機関は、信用情報機関に照会することで、個人のブラック情報を確認することができます。そして、その人の支払い能力に応じた適正な契約の締結や、多重債務の未然防止に役立てているというわけです。
日本の信用情報機関は下記の三つの組織があります。管理している個人の信用情報は、それぞれ違いますが、ブラックリストの情報は3社で共有されています。そのため、債務整理の手続きをおこなうと、すべての信用情報機関にその履歴が登録されます。
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジット会社、信販会社 |
|---|---|
| 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融、クレジット会社、保証会社 |
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行、銀行系カード会社 |
ブラックリストに登録される期間は?
債務整理をしてブラックリストに登録されても、一定期間が経過すると事故情報が削除され、ブラックリストから解除されます。
ブラックリストに登録される期間(事故情報が削除されるまでの期間)は、以下のように信用情報機関ごと、また債務整理の種類ごとに異なります。
| 信用情報機関 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| CIC | 完済日から5年 | 完済日から5年 | 破産手続開始決定日から5年 |
| JICC | 完済日から5年 | 完済日から5年 | 破産手続開始決定日から5年 |
| KSC | 代位弁済日から5年 | 再生手続開始決定日から7年 | 破産手続開始決定日から7年 |
登録された事故情報は3社で共有されますので、信用情報機関ごとにブラック期間にバラつきが生じることはありません。
ブラックリストに登録される期間は、任意整理では完済日から約5年、個人再生では裁判所の再生手続開始決定日から約7年、自己破産では裁判所の破産手続開始決定日から約7年が目安となります。
以下で、債務整理の種類ごとに詳しく解説します。
任意整理では完済日から5年
代位弁済から5年が経過すると、KSCに登録された事故情報は削除されます。そのため、任意整理をした債権者が銀行系の金融機関のみのケースでは、完済から5年以内でも事故情報が消えることもあります。
なお、信用情報機関のデータベースに事故情報を登録するのは、各債権者です。CICやJICCでも、債権者によっては任意整理の和解が成立した時点で事故情報を登録し「契約終了」として取り扱うこともあります。その場合には、「和解日から5年」で事故情報が削除されることになります。
任意整理の場合は特に、債権者次第で「いつから5年」なのかが違ってくるということも、知っておかれた方がよいでしょう。
CICでは、任意整理をしたこと自体が事故情報として登録されるわけではありません。しかし、任意整理の手続きを始めると返済をいったんストップすることになるため、「延滞」という事故情報が登録されます。
任意整理で和解した債務を完済するまでは延滞を解消したことにならないため、完済日から5年は事故情報が保有されるのです。
JICCでは、任意整理の受任通知が債権者に届いた時点で、その事実が事故情報として登録されます。そして、任意整理で和解した債務を完済して初めて「契約終了」となるため、完済から5年は事故情報が残ります。
KSCでは、保証会社が債務者に代わって債権者に返済(代位弁済)した時点で、その事実が事故情報として登録されます。銀行からの借金(銀行カードローンも含む)には保証会社がついており、任意整理を始めると代位弁済が行われます。
個人再生では再生手続開始決定日から7年
個人再生の返済期間は3年~5年ですので、CICとJICCに登録された事故情報は、返済開始から最短8年で削除される可能性があります。
CICでは、やはり「延滞」の解消から5年は事故情報が残ります。個人再生の場合は、再生計画どおりに債務を完済したときに延滞解消となりますので、「完済から5年」で事故情報が削除されます。
JICCでは、やはり「契約終了」から5年は事故情報が残ります。個人再生の場合は、再生計画どおりに債務を完済したときに契約終了となりますので、CICと同様に「完済から5年」で事故情報が削除されます。
KSCでは、個人再生の場合は「官報情報」として再生手続開始決定日が事故情報として登録されます。この事故情報は、再生手続開始決定日から7年間残ります。
自己破産では破産手続開始決定日から7年
自己破産の場合は、CIC・JICC・KSCとも、破産手続開始決定日が事故情報として登録されます。この事故情報は、CICとJICCでは5年経過後に、KSCでは7年経過後に削除されます。
したがって、債権者の中に銀行系の金融機関がない場合は5年、ある場合は7年でブラックリストから解除されるということです。
自分の信用情報がブラックかを確認する方法
信用情報機関に、「自分の借金総額・残債額はいくらか」「ブラックリストに載っているか」ということを確認するために個人信用情報の開示請求をすることができます。
「本人」「弁護士などの代理人」「法定相続人」であれば開示請求することが可能です。それぞれの信用情報機関に直接開示請求をおこなえば「信用情報開示報告書」が発行されます。
開示される情報は「氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先」といった身分に関わる情報と「契約年月日、契約額、利用限度額、債務整理、破産、保証契約、強制解約」といった具体的な信用情報が主なものです。
開示請求はインターネット、郵送、窓口から可能で、必要なものは手数料約1,000円と本人確認書類です。
それぞれの信用情報機関のホームページに開示請求の方法は詳細に説明されていますので、気になる方は請求してみるとよいでしょう。
ブラックリストが及ぼす生活への影響と対処法
- クレジットカードの問題はデビットカードや家族カードの利用で解決できる
- 債務整理後にローンを組んだり借入れを行うのはオススメできない
- 任意整理を選択すればマイホームを手放す必要は無い
- 債務整理後の引っ越しは「家賃保証会社」を通さない物件を選ぶと契約できる
ブラックリストに載ると生活への影響は少なからずありますが、その代表的なものについてご説明します。
また、そのデメリットを最小限におさえる対策方法もありますので、あわせて紹介します。
クレジットカードの新規取得・使用ができなくなる
ブラックリストに載ると、新たなクレジットカードの契約・取得は極めて困難になります。審査がゆるいと言われているカードでも新規作成は難しいでしょう。
現在所持使用しているカードは使用停止となります。そのため、これまでクレジットカードで公共料金や携帯料金などを支払っていた場合には、違う決済方法に切り替える必要があります。
クレジットカードが作れない・使用できなくなるのはデメリットではありますが、以下のような方法でカード決済の代替えをすることが可能です。
カードに変わる決済手段を使う
債務整理をした後は「現在使用しているカード決済ができなくなる」「約5年間は新規カード作成をできない」ということを見越して別な決済手段を準備する必要があります。
具体的には以下のような方法で決済することができます。
【クレジットカードに変わる決済手段】
- 現金払いにする
- 銀行引き落としにする
- コンビニ払いにする
- プリペイドカード払いにする
- 電子マネー払いにする
- スマホ決済にする
デビットカードを作成・利用する
デビットカードは、銀行とリアルタイムでつながっており、決済と同時に銀行口座から引き落とされる仕組みのカードです。大手カード会社のVISA、マスターカード、JCBなどもデビットカードを発行しています。
デビットカードの中には、携帯電話、公共料金の支払いが可能なカードもあります。買い物や食事の決済にも問題なく使用できます。カードの外観は通常のクレジットカードと変わらないため十分代替えが可能です。
ただし、大手カード会社の場合は、ブラックの状態では審査に通らない可能性があります。しかし、楽天カード、住信SBIネット銀行などは、無審査でデビットカードを作ることができます。
家族カードを作成・使用する
主契約者が債務整理した人ではなく家族であれば、「新たに家族カードを作成する」「継続して利用する」ことができます。家族カードの場合、審査の対象は主契約者になるので、債務整理した人であっても家族カードを利用できます。
ローンを新規に組めない・借入れができなくなる
債務整理を行いブラックリストに載ると、新たにローンを組んだり、消費者金融をはじめとする金融機関からの借り入れが困難になります。
ブラックになるということは、「与信力」(経済的な信用度)が大きく低下するので、金融機関も返済能力を疑わざるを得ないからです。
ローンの新規契約や借入れができないことに対しては、以下のような対策をオススメします。
新たな借金をせずに借金完済を目指すこと
債務整理のそもそもの目的は、借金を減額・減免して借金を整理し、普通の生活を取り戻すことです。
新たにローンを組めば借金が増えるだけですので、「ローンを組めない」「借入れできない」ことをマイナスに考えずに、まずは借金完済を目指しましょう。
任意整理は住宅ローンに影響せずに手続きができる
よく誤解されるのが任意整理をおこなうと現在組んでいる住宅ローンに影響するのではというものですが、住宅ローンを残したまま任意整理をすることは可能です。
任意整理をする際に住宅ローンを除いて手続きをおこなえば、マイホームを手放すことはありません。
また、約5年後にブラックリストが解除された場合には、新たに住宅ローンを組むことも可能です。ただし、金額が大きくなる場合は審査が厳しくなるため、できるだけ頭金を増やしてローンの額を減らすなどの工夫が必要です。
賃貸物件の契約ができない
債務整理を機に、家賃負担を減らすため引っ越しを検討する方もいると思います。
その際、通常の賃貸物件の契約の場合、信用情報機関に照会がおこなわれることはありませんので心配は不要です。
しかし、最近の賃貸住宅の中には、家賃保証会社を連帯保証人にする物件が増えてきています。
そのような物件は、契約時に信用情報機関に照会がおこなわれるため、ブラックリストに載っている場合は審査に落ちる可能性が高くなります。
したがって、家賃保証会社を通さない賃貸物件を選ぶようにしましょう。
スマホを分割払いで購入できない
ブラックリストに登録されている間は、携帯電話やスマートフォンの端末を分割払いで購入することはできません。
なぜなら、分割購入もローンの一種であるため、事故情報が登録されていると審査に通りません。
ただし、一括払いの場合は信用情報を確認しないため、端末を購入することが可能です。
ブラックリストに登録されていても、利用料金を延滞していない限り、携帯・スマホの通信契約は支障なくできます。
新規契約や機種変更などで新たな端末が必要となった場合は、以下のような購入方法を検討しましょう。
- 安価な機種を一括払いで購入する
- 中古端末を一括払いで購入する
- 家族の名義で分割購入する
他人の借金の保証人になれない
ブラックリストに登録されている間は、他人の借金やローンの保証人となることはできません。なぜなら、契約の際に個人信用情報を照会されるからです。
保証人は主債務者(借金をする本人)が返済できなくなった場合に返済義務を負うことから、金融機関は契約前に保証人の支払い能力も審査するのです。
住宅ローンや事業資金のローンなどで連帯保証人を求められることがありますが、例えば夫名義でローンを組むときに、妻がブラックリストに登録されていると連帯保証人になれないことに注意しなければなりません。
ただ、最近は住宅ローンでも事業ローンでも、保証人不要の商品が多くなっていますので、配偶者がブラックリストに登録されていてもローンを組める可能性は十分にあります。
また、ご自身がブラックリストに登録されている場合、友人や知人などから保証人を頼まれたときに断る理由にできるというメリットもあります。
なお、賃貸住宅の保証人や、身内の方が入院する際の保証人などは、ブラックリストに登録されている人でもなれます。これらのケースは借金でもローンでもないため、信用情報を照会されることはないからです。
奨学金の保証人になれない
他人の借金の中でも、子どもの奨学金の保証人になれないという点には特に注意が必要です。
子どもが大学などに進学する際に奨学金を借りる家庭は多いですが、親が債務整理をしてブラックリストに登録されていると、保証人になることができません。奨学金も借金の一種であるため、保証人については個人信用情報を照会されるからです。
ただし、親がブラックリストに登録されていても、以下の方法では奨学金を借りることができます。
- 配偶者を保証人とする
- 機関保証制度を利用する
機関保証制度とは、身内の人が保証人となるのではなく、保証機関による保証のもとに奨学金を借りることができる制度のことです。一定の保証料が奨学金から差し引かれてしまいますが、親の信用情報とは無関係に利用可能です。
社内ブラックにより再度の借入ができなくなる
債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるのと同時に、各債権者の社内データにも事故情報が保管されます。
信用情報機関に登録された事故情報は5年~7年で削除されることになっていますが、社内データは各債権者が独自に管理するものであるため、このような決まりはありません。一般的に、信用情報機関から事故情報が削除された後も社内データには事故情報が残り続けます。
そのため、ブラックリストから解除された後も、債務整理の対象とした金融機関に融資を申し込むと基本的に取引を断られてしまいます。このことを「社内ブラック」といいます。
ただ、社内データに事故情報をいつまで保管しておくのかについては、金融機関ごとに取り扱いが異なります。
大手の消費者金融では半永久的に保管していると言われており、そうであるとすれば、その消費者金融からの借入は二度と利用できない可能性が高いといわざるを得ません。
一方で、中小規模の消費者金融や一部のクレジットカード会社では、事故情報を10年程度しか保管しないところもあるようです。
そもそも融資に応じるかどうかは、各社が審査の結果で判断することですので、「一度、債務整理をした金融機関は二度と取引できない」と一概にいうこともできません。
一般的には、社内ブラックの影響で同じ金融機関を再度利用することは難しいですが、中には将来的に利用可能となる消費者金融やクレジットカード会社もある、と考えておくとよいでしょう。
ブラックリストでも影響が無いこと
債務整理をしてブラックリストに登録されると、これまでご紹介してきたように生活への一定の影響が生じることは避けられません。
しかし、ブラックリストの影響は基本的に上記の事柄に限られ、他のことに影響は及びません。したがって、ブラック入りを過度に恐れる必要はないのです。
以下の事柄は、ブラックリストによる影響があると思われがちですが、実際には影響ありませんので、ご安心ください。
保険は加入できる
生命保険に加入すると毎月の掛金の支払いが必要となりますが、借金ではありませんので、契約の際に信用情報機関に個人情報を照会されることはありません。
万が一、掛け金が支払えなくなると契約を解除される可能性はあるものの、保険会社が損失を被るわけではありません。したがって、ブラックリストに登録されていても、掛捨型はもちろんのこと、積立型であっても生命保険への加入は可能です。
積立型で掛け金の支払いを続けると「契約者貸し付け」が可能となります。契約者貸し付けは、ブラックリストに登録されている人も利用可能です。
なぜなら、契約者貸し付けは保険の解約返戻金を担保としており、その金額の範囲内でのみ貸し付けられるため、審査が行われないからです。
なお、生命保険の他にも、損害保険、火災保険、地震保険など、保険の種類を問わず信用情報とは無関係に加入できます。
銀行口座は開設できる
金融機関との取引であっても、預金や送金、給料の受け取りなどの口座取引は支払い能力とは無関係であるため、ブラックリストに登録されていても行えます。
そのため、債務整理後でも銀行口座を新規に開設することは可能です。店舗を有する銀行でも、ネット銀行でも、自由に口座を開設できます。
ただし、ブラックリストに登録されている間は、クレジット機能付きのキャッシュカードは作成できないことに注意が必要です。デビット機能付きキャッシュカードなら作成できます。
各種投資はできる
近年は、「老後の資金を蓄えたい」「効率よくお金を増やしたい」といった思いから、投資を行う人が増えています。
投資には、株式、FX、投資信託、暗号資産(仮想通貨)、ゴールド、外貨預金などをはじめとして多種多様なものがありますが、どのような投資でも信用情報とは無関係に行うことができます。投資は借金ではなく、手持ちのお金で行うものだからです。
銀行口座と同様に証券会社の口座も、ブラックリストに登録されていても開設できます。
ただし、当然のことですが、ブラックリストに登録されている間は、投資資金を得るために借金をすることはできません。
手持ちの資金で投資する場合も、リスクの高い投資には注意しましょう。借金を完済し、経済的に余裕ができるまでは、iDeCoやNISAなどの手堅い投資がおすすめです。
結婚はできる
ブラックリストに登録されていても、結婚することに支障はありません。債務整理したことやブラックリストによって婚姻が制限されるという法律の規定はありません。
婚姻後に配偶者にブラックに登録されていることがバレたとしても、それを離婚原因とすることは法的には認められないのです。
ただし、ブラックリストから解除されるまでの間は、以下のような事情によって結婚生活に支障をきたす可能性はあります。
- クレジットカードが使えないため各種料金の決済に不便が生じる
- 住宅ローンが組めない
- 車のローンが組めない
- 賃貸物件の契約や更新ができないことがある
夫婦間のトラブルを回避するためには、できることなら結婚前に債務整理をしたことやブラックリストに登録されていることを婚約者に伝えて、理解を求めた方がよいでしょう。
知人や職場にはバレない
信用情報機関に登録された個人情報は、金融機関が顧客の支払い能力を審査するために照会した場合を除き、第三者に開示されることはありません。
したがって、ブラックリストに登録されていることが、知人や職場など周囲の人にバレることはほとんどありません。
例外的にバレる可能性として考えられるのは、次の2点です。
- クレジットカードが使えない
- 官報を見られる
飲み会や買い物をする際にクレジットカード払いをしないことで不審に思われることもあるかもしれませんが、「現金払いをモットーとしている」などと言っておけばよいでしょう。
会社でクレジットカードの作成を勧められることもあると思いますが、「クレジットカードは持たない主義です」などと言って断ることもできます。
官報とは政府が発行する日刊紙のことですが、個人再生または自己破産をした場合には氏名や住所が掲載されます。
一般の人が官報を見ることはまずありませんが、金融機関や不動産会社など一部の職種の方は、職場の人に見られてしまう可能性があります。ほとんどの人は、官報への掲載を気にする必要はほとんどありません。
家族への影響はない
信用情報は個人単位のデータですので、ブラックリストに登録されたとしても、家族の信用情報に傷が付くことは一切ありません。
また、債務整理も個人単位の手続きなので、家族の財産が処分されることはありませんし、保証人となっていない限りは家族が返済請求を受けることもありません。
ローンが組めない、子どもの奨学金の保証人になれない、などの事情で間接的に家族の生活に影響が及ぶことはあっても、以下のような心配は不要です。
- 家族がクレジットカードを使えなくなる
- 家族がローンを組めなくなる
- 家族の銀行口座が凍結される
- 子どもの就職や結婚に支障をきたす
ブラックリストのデメリットより債務整理のメリットの方が大きい
ここまでお読みになって、ブラックリストには一定のデメリットがあるものの、影響がない事柄も多いですし、デメリットを最小限に抑える方法もあることがおわかりいただけたことでしょう。
実際のところ、ブラックリストのデメリットを恐れて借金を放置するよりも、債務整理で解決する方が格段に得策です。
以下の点で、ブラックリストのデメリットより債務整理のメリットの方が大きいといえます。
- 任意整理と個人再生では借金を減らせる
- 自己破産では借金をゼロにできる
- 過払い金が戻ってくることもある
- 債権者からの裁判や差し押さえを回避できる
- 借金問題を解決することで経済的にも精神的にも余裕ができる
- ブラックリストから早期に解除される
- 弁護士や司法書士に依頼すれば受任通知の送付により督促が止まる
借金の滞納を放置すると、遅延損害金が加算されて返済額が膨らんでしまいます。それに、滞納が続くと、どのみちブラックリストに登録されてしまいます。
債務整理で借金問題を解決すれば、一時的にはブラックリストに登録されるものの、5年~7年で解除が可能となります。
ブラックリストのデメリットが気になる方こそ、弁護士・司法書士に相談することを強くおすすめします。状況に応じて最善の解決策を提案してもらえるので、希望を見出すことができるでしょう。
まとめ
「今すぐ債務整理をするか?」「ブラックリストを回避したいのでやめるか?」それは、個人の判断です。
ただし、一つ言えるのは、借金返済の目処が立たないのに、それをそのままにすると借金はどんどん膨らんでいくだけです。
そうなると、最初は任意整理で解決できた借金が、個人再生や自己破産の手続きを選択せざるを得なくなります。先延ばしにすることで、借金に苦しむ時間は確実に長くなります。
返済が難しいと感じたら、できるだけ早期に債務整理をするのが得策と言えます。債務整理の手続きは司法書士・弁護士に依頼して早期の解決を目指しましょう。